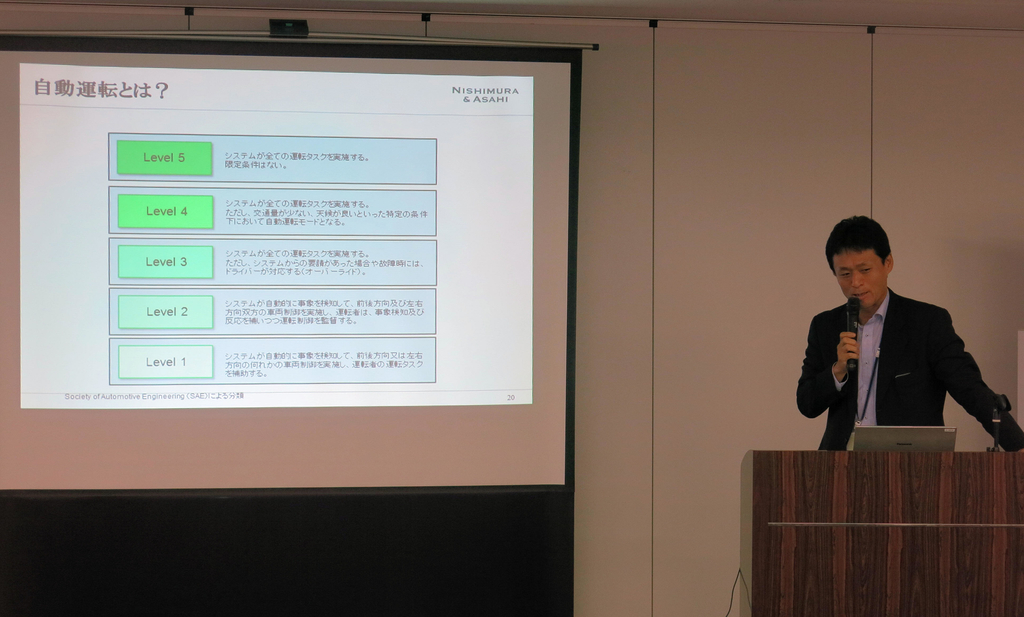『台湾海峡 一九四九』は、台湾人の心の琴線に触れる迫害や闘争の歴史が、物語やルポ、インタビュー、ときには母が息子に語りかける形式で描かれ、美しい文体と技巧に富んだ構成が読者の心をつかむ作品。
台湾、香港での驚異的ベストセラーが意味するもの
「一降りの刀で頭を真っ二つに切られたときの「痛み」をどう正確に記述するのか?」と、記憶により再現できない歴史の限界をショッキングな表現で物語る一方で、ドイツ人とのハーフである息子のフィリップに、1945年、2,000万人のドイツ人が旧ドイツ領から追放され「よそ者」として扱われてきた歴史を、台湾人が1949年に大陸から逃れ「外省人--よそ者」として扱われてきた歴史と重ね、冷静な口調で語りかける。
1948年の中国人民解放軍による長春の包囲戦で発生した30万の餓死者数を掲げ、「これほど大規模な戦争暴力でありながら、どうして長春包囲戦は南京大虐殺のように脚光を浴びないのか?」「どうして長春という都市は、レニングラードのように国際的知名度のある歴史都市として扱われないのか?」と、日本とロシアの歴史を重ね、民族間に共通する欺瞞を投げかける。
台湾および香港では42万部を販売する空前のベストセラーとなり、奥付には多くのページを割き読者の感謝の言葉や感想文が掲載されている。
国連から脱退し名目上世界からは国家として認められていない台湾。中国が我が国の一部だと暗黙の主張をしてはばからない台湾。そういった意識に取り巻かれた台湾の人に、このベストセラーはどういった意味を持つのだろうか。
龍應台という名実共に力のある作家が長い時間と莫大な費用のもとで『台湾海峡』を書き上げ、2009年に発刊された。そして3年後、政府に招かれ、初代文化省大臣になる。
小説家が歴史書のベストセラーを書き政府の大臣になるというキャリアパスを知り、この作品の意図と政府の意図の交点らしきものを見た。本書は読書会のテーマに取り上げられたのだが、そこで「意図の交点らしきもの」を口にすると、参加者の一人から、「龍應台はこの本でナショナルヒストリーを作ろうとしたのだろう」という意見を聞いた。これによりいままでの疑問や考えのすべてに筋が通った。
共同体は人間の「意識」の中にしかない
この本と並行し、ベネディクト・アンダーソンの『想像の共同体』を読んでいた。
国家や民族といった共同体はそもそも人間の意識の中にしかなく、その意識は宗教や言語、教育、物語、地図、博物館などの外的要素で作り出されるという理論。古今東西(とりわけ東南アジア)の膨大な資料や情報を(いささかペダンチックに)引用し、その理論の正当性を証明している。
龍應台は『台湾海峡』という「物語」(ナショナルヒストリー)を通し、台湾人という民族の意識を作るという明確な意図があった。台湾人はこの本により、想像の共同体の一員となったともいえる。
歴史とは事実の積み重ねではない。
歴史には合理的な意図がある。
日本人のナショナルヒストリーを考えてみた。
渡来人の飛鳥文化、貴族と文学の栄えた平安時代、弱肉強食の戦国時代、徳川幕府による国家統一、鎖国、明治維新と開国、アジア帝国主義、軍国主義、原爆投下、敗戦、平和国家としての奇跡の復興、西欧への仲間入り、日米同盟、高度成長、先進国化、大震災、成熟社会……。
こうしたキーワードを使い、日本人のナショナルヒストリーはさまざまなメディアで書き上げられている。
震災を境にナショナルヒストリーを再構築する日本
たとえば8月21日、24年5ヶ月の編纂期間を経て完成した『昭和天皇実録』が、天皇・皇后両陛下に献上された。2015年からの出版を控え、現在その原稿は版元の落札を待っている。ここで、昭和という歴史が改めて物語として編集される。上記のようなキーワードで、日本人の新たなナショナルヒストリーが書き上げられる。私が生きて、見てきた昭和とは、まったく異なった物語が編み出されるに違いない。
その一週間前の8月12日には、ロシアが国後島および択捉島を含む北方領土地域で1,000人規模の軍事演習をはじめている。日本政府が抗議するにいたり、事実上プーチン氏の来日がご破算になった。南に目を向ければ尖閣諸島を挟んで日本と中国、台湾が一触即発のにらみをきかせており、国民が「日本人とはなにか」という自問自答に駆られる材料がメディアを通して軒並み並べられている。
これに呼応した形で、8月23日、陸上自衛隊は東富士演習場で「離島奪回」という非常にタイムリーな目標を想定した実弾演習を実施している。演習に参加した自衛隊員らは約2,300人。戦車や装甲車約80両、火砲約60門、航空機約20機、使用した弾薬は3億5,000万円分で実に44トン。過去最大規模である。
メディアを賑わせる北方領土や尖閣諸島の問題を背景に、離島奪回を想定した過去最大規模の実弾軍事演習と、『昭和天皇実録』完成のタイミングは、決して偶然ではない。
日本はいま、ナショナルヒストリーを再構築している。これにより民族意識を新たに構築しようとする動きが、報道を通して強く伝わってくる。
政府は7月1日、集団的自衛権を行使するべく憲法解釈を変更した。自衛隊の「自衛」の解釈の幅が広まることは、軍事活動の範囲が拡大することへの強い懸念材料だ。この「自衛」という言葉がくせ者であることは歴史が証明している。ときには、攻撃や侵略という言葉とすり替わる危険性がある。
ナチスがポーランドを攻撃したのも、「ポーランドは危険な国だからいまのうちにおさえておく。これは「予防」であって侵略ではない」という根拠だった。
その後戦火は拡大し、第二次世界大戦のきっかけとなりナチスが侵略を繰り返したのは周知の通りである。言葉のすり替えは、いつの時代にも起こっている。
日本が太平洋戦争に突き進んだのも、国民の疑問や不信感を抱えたままでそうなったのではない。戦争にいたるまで計画的にナショナルヒストリーを再構築し、綿密なメディア操作を行い、政府の意図する方向に世論と国民を持って行った。言い換えれば、「戦争以外に選択肢はないのだよ」という方向に世論を運搬した。そうした動きの端緒が最近の日本に見え隠れしているのを感じるのは、私だけでないはずだ。
戦争を抑止する文明の利器としての「メディア」の役割はとても重要
こうした状況下で大切なのは、歴史とメディアを知ること。
歴史において政府はメディアを駆使し、戦争へと流れる集団的意識、つまり世論を作り上げる。こうした歴史が日本と世界に大変な傷を与えたことを忘れてはならない。もちろん、傷を与えたという意味では、勝戦国も同様である。「ああ、またか」と、戦争が決して起こらないよう、国民として世論の流れには注意深く目を向けていく必要がある。
ネットや機器の発展でメディアがあらゆる人へと普及した昨今、これらは戦争を抑止する文明の利器である。そう、私は信じたい。
三津田治夫(2014年9月26日の記事から)