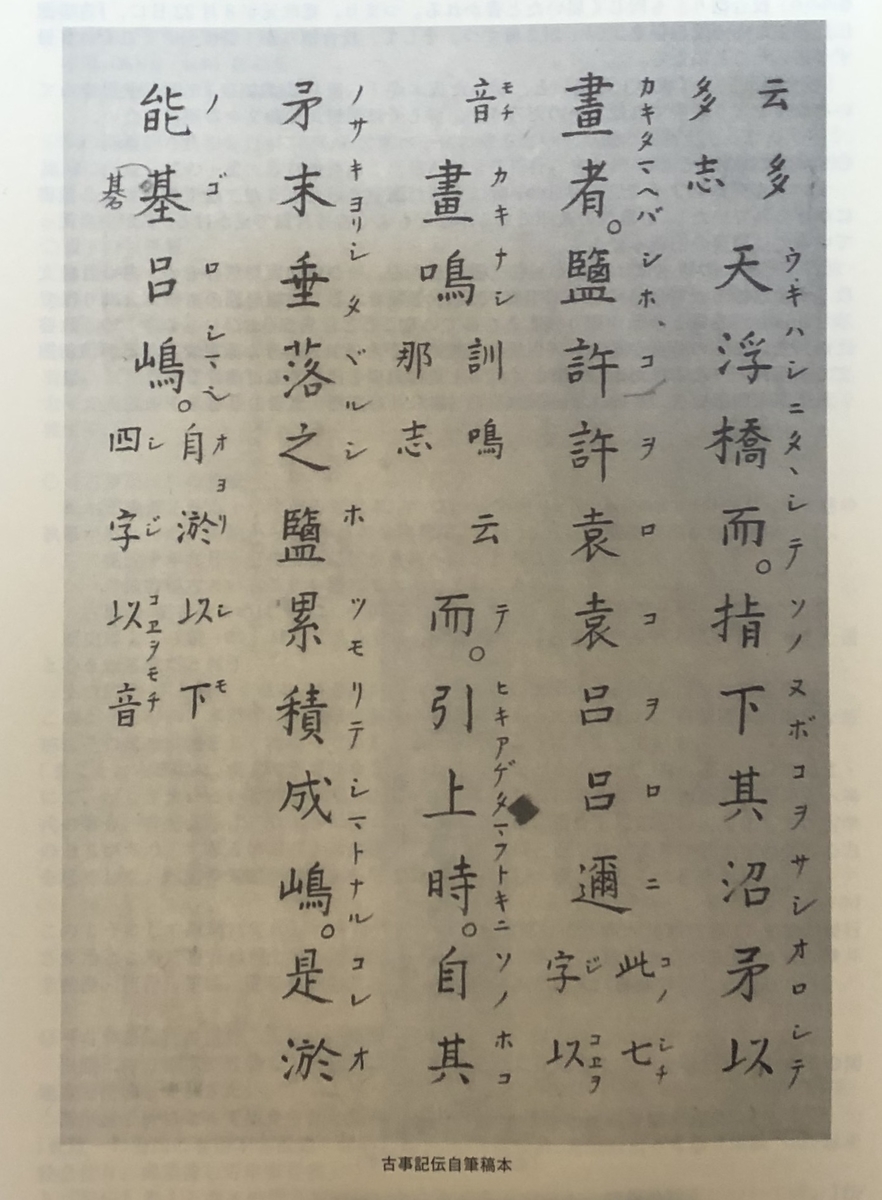『紅い砂』(高嶋哲夫 著、幻冬舎刊)は、元米兵ジャディスが率いる革命軍が内戦で中米コルドバの政権を奪取し、民主主義国家を樹立する、という物語だ。
独裁政治と薬物による暗黒経済が支配するコルドバの国民は、自由を得ようと、メキシコとの間に米国が築いた9メートルの「壁」を乗り越えようとする。
そこで発せられた一発の銃声から銃撃戦が始まる。女や子供たちなど多くのコルドバ国民が射殺される。この悲劇が物語のはじまりであり、物語の中心軸をなしている。
米国版での発刊が決まっており(英題:『The Wall』)、また本作品を脚本にしたハリウッドでの映画化が計画されている。
映画の台本として書かれただけありスケールが壮大で、臨場感が高い文体とともに、戦争と革命の場面に置かれたような錯覚を得る。
革命と平和、抑圧と自由という、平和な日常では考えることの少ない、人間の本質にかかわる問題を私は受け止めた。
いま、私たちの平和な日常は一変した。
私たちは自由を求めて、ウイルスという見えない敵との戦いに直面している。
そして私たち人類は、いつ来るかわからない見えない敵に備えた世界のリフォーム「革命」を行おうとしている。
いま、『紅い砂』が投げかけるメッセージは、心に深く食い入ってくる。
1988年に見た、革命前夜の東欧の姿
私は偶然、1988年、東欧革命の前夜を体験する機会があった。
『紅い砂』を読んでいると、作品の描写と東欧革命の体験がオーバーラップして頭から離れない。作中に登場する、メキシコとアメリカの国境に建造された「壁」がそれである。
東西社会の分断の象徴としてかつて存在したベルリンの「壁」のイメージを何度も重ね合わせた。
作品で描かれる「壁」は、政治経済と同時に、人間の心の流通を分断する。
この構造は、東西社会を分断していた「壁」とまったく同じである。
私が東欧に初めて足を運び入れたのは、1988年のことだった。
単に「飛行機を使わずドイツに行ってみたい」という冒険心から、バックパッカーとして日本をたった。
船舶で中国の上海かソ連のナホトカに行き、そこから列車で移動する必要がある。迷いながら、とくに深く考えず、ナホトカ港行きの旅客船、コンスタンチン・チェルネンコ号に乗り、横浜から出航した。
ナホトカ港に着きハバロフスクまで列車で移動。そこからシベリア鉄道でモスクワまで移動した。
 ◎コンスタンチン・チェルネンコ号の乗船パンフレット
◎コンスタンチン・チェルネンコ号の乗船パンフレット
当時はソビエト連邦が東側社会の中心として政治経済を掌握していた。
私が通う大学ではマルクス主義、共産主義を連呼する学生運動の立て看板が随所に掲げられていた。共産主義に対する淡い夢と希望が、日本社会のどこかにまだ存在する雰囲気すらあった。
しかし私がハバロフスクからモスクワに行くまでの陸路で見た現実は、一度も体験したことのない極度の貧困であった。
食糧不足である。
そして、物不足。
 ◎当時のソビエト連邦大使館で配布していた機関紙『今日のソ連邦』
◎当時のソビエト連邦大使館で配布していた機関紙『今日のソ連邦』
シベリア鉄道がモスクワに近づくにつれて、一日一日、食堂車からメニューが消えていく。
車両ですれ違うロシア人たちは、日本人を見るとコンパートメントに引き入れ、ホンダやソニーというブランド名を連呼し、「日本にはこうしたものがあふれているのか」と質問攻めをする。私も何度も質問された。
首都のモスクワに行っても物不足。
パン一つ買うにも半日は行列に並ぶ必要があった。
モノとコトの流通が分断された社会
モスクワからワルシャワに移動し、そこからクラコフ(ポーランド)、プラハ(旧チェコスロバキア)、ブダベスト(ハンガリー)、ベオグラード(旧ユーゴスラビア)、ブカレスト(ルーマニア)、ソフィア(ブルガリア)、イスタンブール(トルコ)へと移動し、イスタンブールからパキスタン経由で日本に帰国した。2か月の旅だった。
当初はワルシャワ、プラハ経由で西ドイツに行く予定だったが、あまりにも衝撃的な光景が多く、また、東欧諸国の人々の日本人である私に対する強烈な好奇心の高さで(私はいつもどこかで誰かしら現地の人間と接触していた)、私自身の好奇心と相まって、私は東欧を出ることがなかった。
「あまりにも衝撃的な光景」とは、食糧不足と物不足に加え、情報不足である。
いわば、モノとコトの流通が遮断された社会である。
西側の経済制裁と東欧経済の破綻、さらに東欧諸国の情報統制により、自由に行き交うモノと情報がほとんどない。
なかなかイメージしづらいが、ロシアと東ヨーロッパ全体が、いまの北朝鮮のような状態、と考えればわかりやすいだろう。
あの広大な大陸が北朝鮮状態だったのである。
 ◎東欧革命前のポーランド通貨「ズウォティ」紙幣。肖像は天文学者コペルニクス
◎東欧革命前のポーランド通貨「ズウォティ」紙幣。肖像は天文学者コペルニクス
ポーランドでは、ワルシャワでもクラコフでも、パン一つ買うのに半日以上行列に並んだ。
最低限の食料を手に入れるにも、この状態だった。
一方で「闇ドル」も存在した。
米ドル紙幣を、裏通りを歩く「闇ドル換金者」たちに渡すと、通常レートの数十倍で現地通貨(当時の通貨単位「ズウォティ」)に換金される。
またホテルなど外国人が出入りする施設では普通に闇ドルが流通していた。
クラコフではホテルのフルコース料理を闇ドル10ドルで注文した。
物不足の裏には、いびつな闇経済も存在していた。
情報不足は、政府の統制によるものだった。
西側の情報は遮断されていたため、私のような日本人は街を歩いていると市民から声をかけられ、別室で質問攻めにあう。
とくに東側でも当時のワレサ議長による労働組合「連帯」を結成するなど先進的な国であったポーランドではそうしたことがよくあった。ワルシャワ市街では大学生に声をかけられ、彼らの寮に招かれ、5日間毎晩ウォッカを飲みながら、夜中まで日本のこと、自由のこと、民主主義のことを延々と質問され、語り合っていた。
クラコフでは修学旅行の小学生の集団とユースホステルで一緒になった。
ここでも子供たちからは質問攻めだった。そのある夜、屋外から機関銃の発砲音を子供たちと聞いた。子供たちは悲鳴を上げて怖がっていた。日中、マシンガンで武装警備する兵隊(ミリツィア)たちと街中でたびたびすれ違った。おそらく彼らが発砲したのだろう。
(後編に続く)