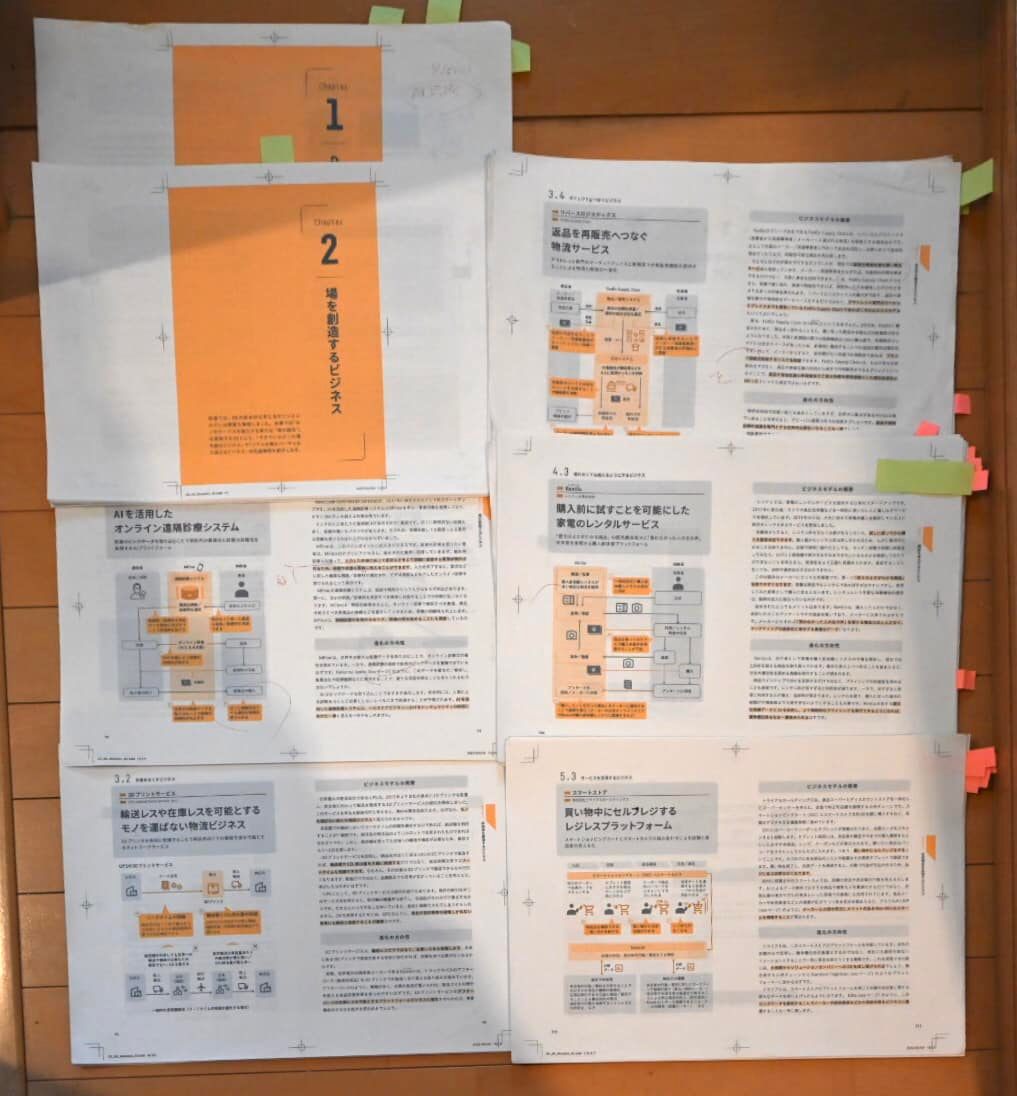今回は初のイタリア文学作品ということで、イタロ・カルヴィーノ(1923~1985年)の作品、『見えない都市』を取りあげることにした。
作品が発表されたのは1972年。
おりしも東西の列強がアジアの都市を奪還しようと火の粉をまきあげていたベトナム戦争のまっただ中であった。
読者を煙に巻く不思議な幻想文学
これはどんな作品かというと、一言で、幻想文学。
マルコ・ポーロは見聞をフビライ・ハンに報告し対話するというやり取りを通し、言葉が都市を形成するという不思議な物語。
「読んでいて眠くなった」「ぼんやりしていた」などの意見が会場からいくつか出てきた。幻想文学にはうってつけな読者の反応とはこういうもので、あたかも読者を煙に巻くかのような描写表現が多々ある。そこはカルヴィーノの作風というか、文学の限界を取り壊そうとした彼のネオレアリズモ作家としての姿勢が貫かれている。
正直私も、読んでいてよくわからなかった。なにがわからないのかというと、「そもそも都市とはなんだ」という疑問。ビデオもカメラもネットもないマルコ・ポーロの時代。「見聞」だけが都市を伝える方法だった。
もちろん、計測したり筆写したりという方法で都市を伝えることもできる。しかしそれも見聞の域を脱しない。
私は東京都で働いているので、東京という都市を知っている。それは、子供のころから「東京は日本の首都です」と習っているから知っている。であれば、都市とは教育なのか、ということになる。そう考えると、都市とは言葉である、とも言える。あるいは、私は東京都で働くという体験を持っているので、東京が都市である、と認識しているのかもしれない。となると、都市とは体験なのか、という話になる。
マルコ・ポーロはあるのだかないのだかよくわからない都市の見聞を、さもありなんとフビライ汗(カン)に報告する。
そしてフビライの「朕の夢はただ精神か、さもなくば偶然の作りだしたものなのだ。」という独白に対してマルコ・ポーロは、「都市もまた、精神か偶然の産物であると信じられております。」といったように、答えになっているのだかなっていないのだかわからない曖昧な返答をする。それもあってかフビライは、「……つまるところ、そのほうの旅とは、まさに思い出のなかの旅なのだ!」といったいらだちを表明する。
また、マルコ・ポーロの報告する都市にはすべてデスピーナ(ちなみにこれはモーツアルトのオペラ『コジ・ファン・トゥッテ』に登場するキーパーソンの女中名と同じ)やフェドーラ(昔Linuxのディストリビューションに「フェドーラ・コア」があった)、ドロテーア、アンドレア、アナスタジアなどの女性の名前がついている。となると「都市とは欲望なのか?」「都市とはイメージか?」という読み方も出てくる。
都市というテーマに仮託したコミュニケーションの物語
物語の後半になってくるとマルコ・ポーロとフビライの対話が半ば崩壊しはじめ、それはフビライの帝国の崩壊を予期させるような退廃的な雰囲気を醸し出す。となると都市とは対話ではないか、とも言えるはずだ。
読みながら会場内で議論を進めていくと、どうも『見えない都市』は、都市という一つのテーマに仮託した言葉の物語、あるいはコミュニケーションの物語なのでは、という結論に達した。
現代社会では、都市には高層建築物があって、自治体があって、商業と居住の空間があって、などの漠然とした定義がある。しかしかつては、都市という定義はなかった。そもそも都市とは概念上のものだったが、近代化と共に「見える化」されてきた。こうした、普段私たちがまったく考えもしなかった問題提起を、作者のカルヴィーノは幻想文学というスタイルで私たちに投げかけてくれた。
最後に、この本を象徴する一文を引用する。
「偉大なる汗(カン)は勝負に没頭しようと努めていた。しかし今ではその勝負の理由が彼の思念を逃れ去ってゆくのだった。ゲームの終わりはつねに勝利かあるいは敗北なのだ。だが何の? その真の収穫は何なのか? 王手をかけ、勝利者の手によって取り除かれる王のあとに残されるのは、ただ黒か白かの枡目ばかり。……すると、究極のその獲物は、帝国の色鮮かな宝物の数々とその幻の外皮にすぎず、ついにはただ滑らかに削った一片の嵌木、無となっているのだった……」
かくも偉大な皇帝フビライが帝国拡大に求める要素は都市でできていて、都市とは見えない概念であり、ゲームの碁盤であり、嵌木であり、無であった、というオチである。
ともかく不思議な作品なので、ぜひ一読いただき、ご賞味いただくことをおすすめする。
作家カルヴィーノについて
ついでに作家について。
イタロ・カルヴィーノは幻想文学から児童文学、文芸評論までをこなす20世紀イタリアを代表する多彩なインテリ。
戦時中はガリバルディ旅団のパルチザンとして反体制運動に関与し、戦後はハンガリー動乱が起こる1956年までイタリア共産党員として活動。
『見えない都市』をはじめ、『まっぷたつの子爵』『木のぼり男爵』『不在の騎士』『レ・コスミコミケ』などの文学作品や、また『イタリア民話集』の編纂も手がけている。
本作を訳した米川良夫(よねかわりょうふ)は、父親が『ドストエフスキー全集』や『戦争と平和』の個人完訳を行ったロシア文学の大翻訳家米川正夫で、兄がロシア文学者の米川哲夫とポーランド文学者の米川和夫、叔母が生田流箏曲家の人間国宝米川文子という、そうそうたる血を引くサラブレッドである。同氏は本作『見えない都市』や『木のぼり男爵』など、カルヴィーノの作品を格調高い名訳で日本人に紹介してくれたイタリア文学者である。
* * *
さて次回は、日本の原点、古典に帰ってみましょうというコンセプトで、最近はやりの親鸞を取り上げてみる。
お題は、『最後の親鸞』(吉本隆明著)と、『歎異抄』(親鸞)の二冊である。
私は数年前吉川英治の『親鸞』を人間親鸞、男性親鸞として面白く読ませていただいたが、はたして吉本隆明の描く親鸞とはどんな人物なのか。興味につきない。
では次回も読書会を、お楽しみに。
三津田治夫