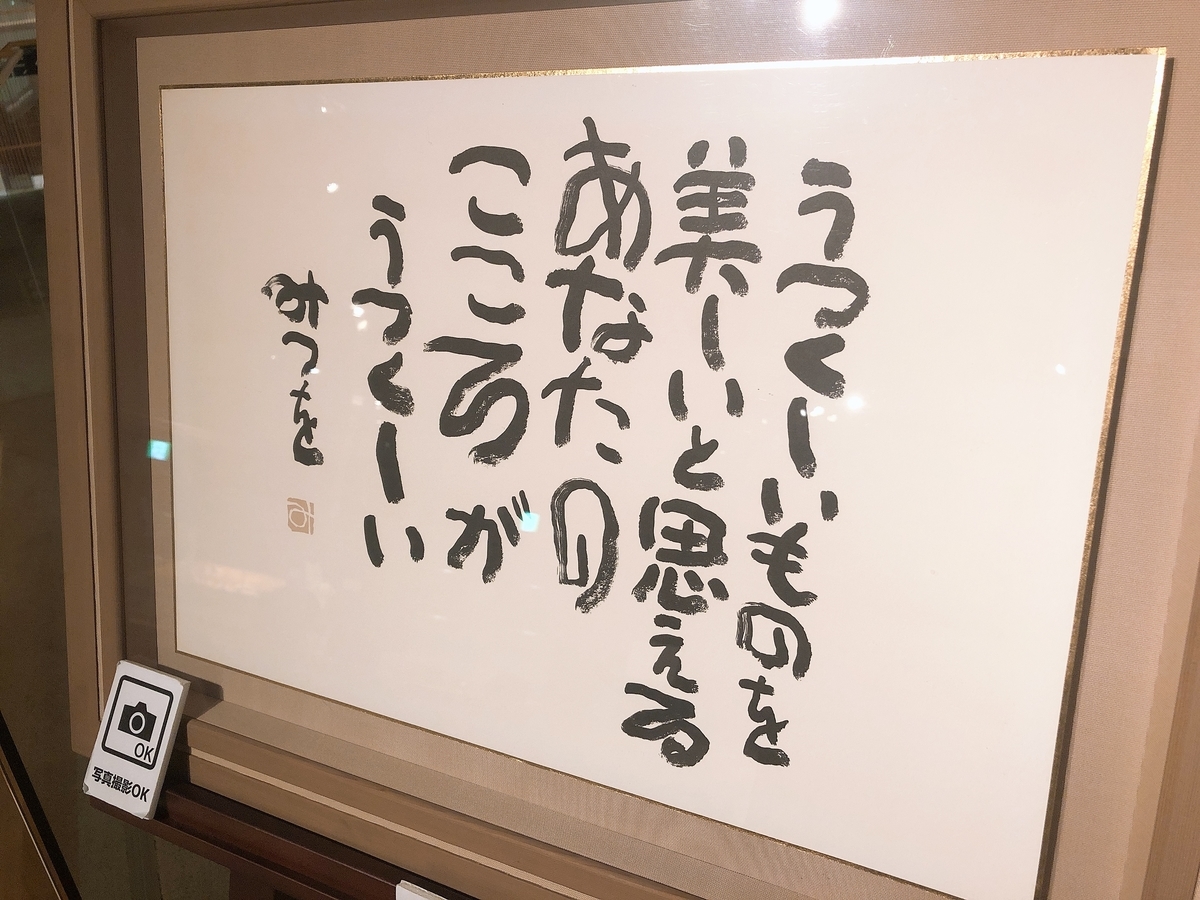(前編から続く)
この作品で、作者が描いた運命のはかなさを誰もが読み取ることだろう。
一つは、救うはずで不本意に殺してしまった「雁」の存在で、これは「鯖の味噌煮」と関係する。鯖の味噌煮も偶然に出てきたもので、これがなければ「私」は岡田を誘って外出しなかった。
偶然通りすがった岡田が瀕死の紅雀に遭遇し、それを救出したのことを、お玉はヘビ(末造)に食われる紅雀(お玉)に自分の姿を重ね合わせ、一気に情熱の炎が燃え上がった。
そうした情熱の炎を、鯖の味噌煮が一気にかき消してしまった、というのである。
これは作者が意図した仕掛けであるが、なんだかどうも、私が読むに、違和感がある。
なにごとにも、当時(明治時代)の読者の神経を鑑みなければいけないが、それにしても、鯖の味噌煮ごときで女(人間)の運命が決定してしまうなんて、あまりにも切なくはないか(この切なさが、この作品の売りでもあるのだが)。
しかしどうも、この作品を冷静に読むと違和感が残る。
最後まで首をひねったのは、あれだけ情熱的になったお玉が、どうして最後になって身を引くような仕草を取ったのか、ということだ。
お玉は、父親のために高利貸しの妾になる決意をしたり、岡田への告白まで男のことをひたすら思い続け、用意周到にその準備までする情熱家だ。
そんなお玉ならば、無縁坂を岡田と「私」の二人が通り過ぎようが、岡田だけを捕まえて「ちょっと」と声をかけてもいいだろう。
もしくは雁を捕まえて帰宅するあとにも、遠巻きに眺めていずに、「私が料理するからうちで雁を食べましょう」と声をかけたっていいだろう。
それだけでも関係に一歩前進が見込まれる。その際に渡欧先の住所を聞いたっていい。
お玉ほどの情熱と積極性があれば、そのぐらいはできまいか。
しかしふと思うのは、岡田の渡欧である。いまとはまったく感覚が異なるから、当時のドイツとは、いまでいう火星とか金星ぐらいの、「まず行けないところ」と考えてよい。
それゆえに岡田とお玉の別れは永遠なのだ。
この作品にはいろいろと考えるところがあるが、明治の文学に一律に感じることは、"不自由"や"制約"である。
人間に向けた制約が異様に多い。
つねに明治の文学がはらむ制約は、「西洋」と感じる。
明治人の西欧への物理的・精神的コンプレックスは、数多くの制約を生んでいた。
漱石は西洋的なエゴイズムに対して呵責ない攻撃を加え、江戸文化への淡い憧憬を抱いた。二葉亭四迷は西洋から入ってきた
官僚社会を、アイロニカルに取り上げた。
そう考えると、鴎外には、西洋文化に対する呵責なき攻撃という、漱石のような激烈な姿勢が見られないのは特徴的だ。
それを踏まえて鴎外の『雁』を読んでみても、西洋へのコンプレックスというものをあまり感じさせられない。
文体は主語述語が明晰で、外国語への翻訳も容易にできるはずだ。
その意味で「世界文学」になる素質も十分にある。
読後感もどことなく西洋文学の雰囲気が香っており(舞台はどう考えても江戸なんだけど)、ウィーンの世紀末文学を思いこさせる。
そういった、鴎外の西欧臭さを読み解く鍵は、鴎外の留学時代の経験にある。漱石と対比してみるとそれがよくわかる。
二人が過ごした留学生活のレベルに天地ほどの差があったのは、有名な話だ。
軍医として1884年(明治17年)からの4年間、ドイツに国費留学した鴎外は、ベルリン、ライプツィッヒ、ドレスデン、ミュンヘンと各都市を歴訪し、細菌学者コッホのもとで研究を行い、学外では社交界と交流し、豪華絢爛な海外生活をおくる。
その間、軍医としても、陸軍一等軍医に昇進したり、プロイセン軍に召還されるなどと業績が認められ、おまけにドイツ人からはモテまくり、ベルリンで妊娠させた女性に日本まで追いかけてこられ、その体験を小説(『舞姫』)にしてベストセラーにまで仕立て上げてしまう。
対する漱石はというと、鴎外が留学した16年後の1900年(明治33年)からの2年間、ロンドンに国費留学したが、鴎外とは打って変わり、生活には華やかさの一片もなかった。
本を買うにも衣食住を倹約するほどの貧困生活が続き、帰国時には心労がたたってノイローゼを発症する。
これだけの海外での貧富の格差が開いたことは、評論家の江藤淳によると、当時の為替レートにヒントが隠されているという。
1895年(明治28年)に日清戦争で日本が勝ち、下関条約により日本は賠償金を手にする。1897年(明治30年)、大金を手にした政府は金本位制の導入に踏み切るのだが、このとき政府は為替レートを、1ドル1円から、1ドル2円という超円安に設定した
(いまでいえば1ドル90円のレートを急に1ドル180円に切り下げるようなもの)。
ちなみに、円安であれば輸出がしやすくなり日本の国力が高まる、というのがその論拠なのだが、円安を異様に歓迎する日本の政財界の意識が、100年以上も昔から綿々と流れ続いているのがよくわかる。
さて、ここでなにが言いたいのかというと、同じ国費で留学していた鴎外と漱石とでは、明治30年に実施された為替レートの切り下げで、海外での貨幣価値に2倍の開きが生じ、これにより、方や貴族のように華々しく、方や極貧、という、極端な経済格差(生活レベルの違い)が発生した。
こうした状況で二人の目に映った西欧像に大きな隔たりがあるのは当然だ、ということである。漱石にしてみればロンドンで人種差別まで体験しているというのだから、なおさらである。
ドイツの各都市で貴族や大学者と交流し、仕事は認められ、白人女性からは引く手あまたで、鴎外はもうなんにもいうことはない。
漱石のように西欧に対する激しい嫌悪感を抱く理由など一つもなく、まさに西欧は鴎外にとってのふるさとであり、あこがれでもある。そういった鴎外の思いを、作品を読みながらひしひしと感じる。
こうしてみてみると、天才たちの運命は、国家の思惑一つと、それに本人が遭遇してしまう歴史的タイミングですべて変わってしまう、ということがわかる。
仮に鴎外がドイツで極貧生活をおくっていたら、帰国後にどんな作品を書いていただろう。完全フィクションだったとしても、『舞姫』を書くことはまず無理だったろう。
そう考えると、ウイーン世紀末文学を想起させる、耽美的な色香が漂うこの『雁』も、鴎外の西欧での「イイ思い」なくして、書くことはできなかったはずである。
(おわり)