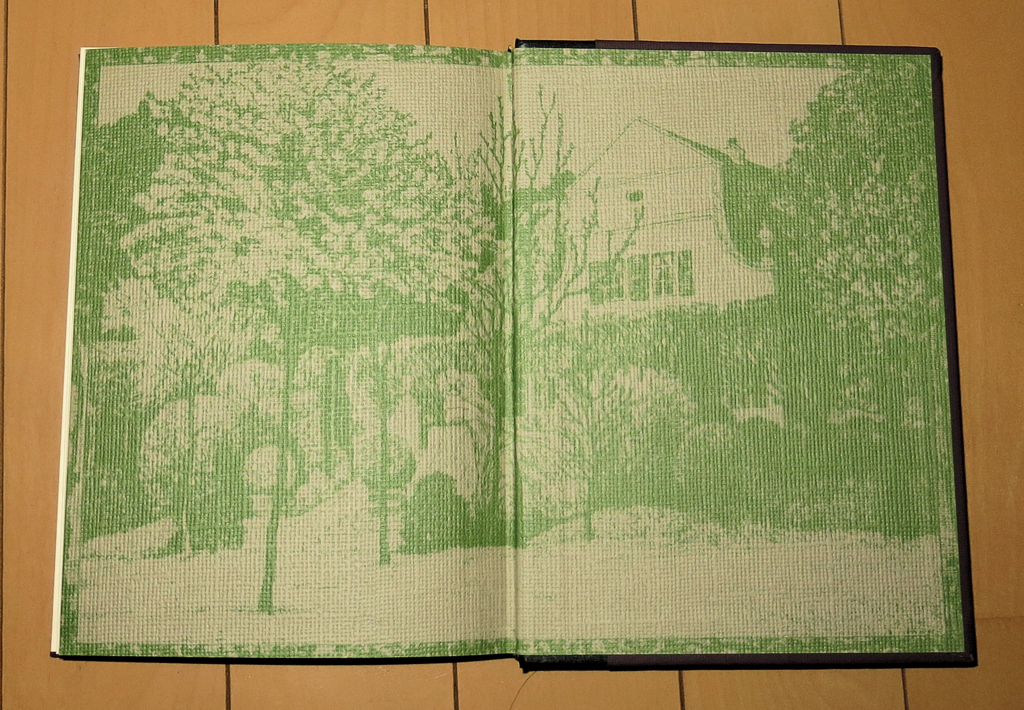3回目のセミナーは再びAIを軸に、今回は「ロボット」をテーマに、TKPガーデンシティPREMIUM秋葉原カンファレンスルームにて開催した。
スピーカーには「AIサービス提供者・プログラマー・エンジニア」という立場からLINE株式会社の橋本泰一氏を、「ロボティシスト・ロボット工学者」という立場から東京藝術大学の力石武信氏をお招きし、異なる才能を持つお二方に登壇いただいた。前者は産業界でサービスを届けるエンジニア、後者はロボットで舞台芸術など社会実装を行う技術系アーティストである。
セミナーの概要とスピーカーのプロフィールなど
https://tech-dialoge.doorkeeper.jp/events/67056
◎会場の様子(TKPガーデンシティPREMIUM秋葉原カンファレンスルームにて)

スマートスピーカーの普及がAIの未来をけん引する
冒頭は橋本泰一氏によるAIの歴史解説。
1956年のダートマス会議からAIという言葉が聞かれるようになり、CやFORTLANなどのプログラミング言語や数々のアルゴリズム、パターン認識の技術が発達してきたことが述べられた。
これにより「コンピュータは知能を持てる」という希望がエンジニアの間で共有され、いわゆる「第一次AIブーム」が起こった。
こうしたブームは出ては消えが繰り返され、第二次AIブームでは日本がエンジニアリングを牽引するも産業的にうまくいかず、研究の主体が再び基礎研究に戻る。
データを中心にした統計学を採り入れたAIの研究が進む中、いま私たちが直面しているのが「第三次AIブーム」である。
◎産業界から生の声を伝える、LINE株式会社の橋本泰一氏

こうしたAIの発展中に登場したのが、日本でもようやく普及を見せつつある「スマートスピーカー」である。
スマートスピーカーはキーボードやマウス、タッチパッドに代わる、音声を使った新しいユーザーインタフェースである。
いわば音声を無差別にモニタリングしているデバイスであり、プライバシーの問題や、デバイスが聞き取った音声は本当に人間のものであるのかという判別の問題も抱えている。
◎橋本氏が語るスマートスピーカーの未来

会場からの質疑応答で、橋本氏はスマートスピーカー開発で苦労した部分として、音声認識をいかに正確に行うかという点、表記が一つで読み方が複数あるという日本語の扱いが非常に難しい点をあげた。
音声認識の精度の高さはスマートスピーカーの性能に直結するため重要な課題であるが、これは時間が解決するはずである。
また日本語の問題はこれはエンジニアリングで解決するしかない。スマートスピーカーの普及が日本で遅れた原因はここにあるが、これもまた時間が解決するだろう。
「AIにおいて機械学習とディープラーニング以外の研究はされているのか」という質問には、いろいろな取り組みがあるが対抗馬は出ていないという回答で、「AIは“知識とはなにか”を理解しているのか?」という質問には、まずは人間が「理解とはなにか」を判定する方法を持つべきだが、まだそれがなく、AIが知識を理解するにはまだほど遠い、という回答が興味深かった。
ロボットを社会実装し、「人間とはなにか」を問う
力石氏には、ロボットと芸術をテーマに話していただいた。
同氏が手がけられた、深田晃司監督のロボットが女優を演じる世界初の非SF映画『さようなら』や、ハンブルグで上演されたロボットが出演するオペラ『海、静かな海』の動画が紹介され、人間の中にロボットが投入されるコントラストで、作品を通して「人間とはなにか? を観客に問いかけている」という考え方が語られた。
◎ロボットの社会実装を語る、東京藝術大学の力石武信氏

「人間とはなにか?」の一つの答えに、「他人を理解する心を持っているもの」があげられる。他人を理解する心とは、ストーリーを理解する心、とも言える。そこで「心とはなにか?」という疑問が出る。知的に振る舞うことと心があることは別である。AIやロボットに知的な振る舞いまではできるが、それ以上は難しい。しかし人間を、「他人を理解する心を持っているもの」であるよう「振る舞っている」生き物であると定義したらどうか。となると、ロボットにも、「心があるように振る舞わせる」という発想が生まれる。この考えのもと、力石氏はロボットの社会実装を行っている。
ロボットを動かすためにセンサーを大量に装着したり、心理学や社会学などの科学的な知識を取り入れても、人間とのコミュニケーションを思うように図ることができなかった。そこに採り入れられたのが、アートの領域である。科学的なことは説明性と再現性が高い一方で、ワクワクやかっこいい、気持ちいい、美しいといった、直感的なものが欠如している。科学的な要素にアートの要素を加えることで、人間とロボットのコミュニケーションの質が高まるのではないかという仮説のもと、科学とアートのバランスを取りながらロボットの社会実装に取り組んでいる。
シンギュラリティは人間の仕事を奪うのか?
後半の質疑応答では、本来ロボットとは人間の労働を代替する装置として定義された言葉だが、果たして、AIとロボットは人間の労働を奪うのか。2045年問題としてシンギュラリティが訪れ、人間の進化は激変するのか。これらに対するスピーカー2人の意見が語られた。
◎力石氏が手がけられた、アンドロイドとのインタラクションシステムの例

まずはシンギュラリティについて。
力石氏は「シンギュラリティは来ない」との見解。
将棋や囲碁の対局もそうだが、人間には人間にしか持ちえない神秘性がある。
AIとロボットは神秘性を持てない。ゆえにシンギュラリティが訪れ、人間を超越するということはないだろう、という。
橋本氏は「来るとも来ないとも言えない」という見解。
いまの流れを見ていると、2020年をピークに「AIって意外とたいしたことないよね」という風潮が訪れるはずで、過去の流れからもAIはブームと衰退を繰り返している。2020年をピークに第三次AIブームが去り、2045年をピークにした次のブームが来るのかというと、それは疑問である。とはいえこの時期には、人間がいままで行ってきた進化とはまた別の方向とスピードで進化を遂げるだろう、との見方だ。
上記見解を踏まえ、AIとロボットは人間の労働を奪うのかという質問に対し、お二方とも条件付きで「それはない」という結論だった。
まず橋本氏は、AIとロボットは「人間の持つ“忙しい”の定義に変化をもたらすだけ」という見方。AIとロボットはいままで人間がやっていた行為を肩代わりするだけで、そうした変化をどの時点でどう受け入れるかが重要である。それには、企業や政府の意向をそのまま受け入れるのではなく、多くのユーザーが広く声をあげ、意見し、AIとロボットがもたらす社会変化をユーザーレベルで最適化していく必要がある。これが、橋本氏の意見である。
力石氏の見解は、経験と分析を繰り返すのはAIの得意分野であり、一方で人間には自分の手がけている行動で理論的に説明のつかないものが山ほどある。ここを磨き、価値にすることが、人間に与えられた課題である。「人間にしかやれないことをやろう」である。
「経験と分析を繰り返すのはAIの得意分野」という意味で、橋本氏は、かつてデータサイエンティストブームが訪れたときに、「AIに代替されていく職種」と予想。実際にそれが実現した。
結論を言えば、2045年にシンギュラリティが来ようが、AIとロボットが人間の労働を肩代わりしようが、「自分たちがどう生きるか」にかかっている。つまり自分たち人間の未来は自分たちが選択するものである。AIとロボットといった周囲の環境に拘束されるものではない。
最後にお二方の話を受け、「AIとロボットがもたらす未来」をテーマに、6つのチームによるグループディスカッションと発表が行われた。最後にお二方の話を受け、「AIとロボットがもたらす未来」をテーマに、6つのチームによるグループディスカッションと発表が行われた。
AIにもロボットにもない、人間ならではの価値を探る
ディスカッション最初のチームは、AIとロボットの普及は所得格差をもたらすはずである。チーム内で就職活動をしているメンバーがいるので、「どの分野に就職すべきかのアドバイスを欲しい」という発表であった。議論の内容が目下の具体的課題に直結した点は興味深かった。AIとロボットは社会の職業マップを大きく塗り替えていくので、そこにも「自分たちがどう生きるか」が問われているはず。就活生にとっては選択に苦しむ厳しい時代だが、見方を考えれば、生き方を多くの選択肢から選ぶことができる自由な時代でもある。
◎グループでのディスカッションを実施
2番目のチームは、AIにコンテキストや意味内容を理解することは不可能なので、意志決定までは無理。「意志決定の領域は人間ならではのもの」という発表だった。AIによる将棋や囲碁のように、もしかしたらAI経営者というものが出てきて、AI経営者同士が収益を競い合う未来がくるかもしれない。
「AIとロボットは道具になるか、よき隣人になるか。そのいずれか」という明快な意見もあった。AIとロボットは道具として人造されたものだから、そのまま使わせていただくか、隣人として愛玩するか、である。自動車はこれに近いだろう。「愛車」という単語もあるぐらいで、自動車もいつしか生活に欠かせない隣人となった。自動車はAIとの融合で、将来はより隣人性が高まるはずだ。
「AIに合わせるように人間が喋るようになるだろう」という見解は、スマートスピーカーに関連する発言だった。AIから結果が返ってくると人間がそれに合わせて話し言葉を最適化する。AIに理解されやすい話し方という、AI時代のコミュニケーション術が確立されるだろう。ビジネスパーソンの間では会話術が永遠のテーマだが、今後は「AIに好かれる会話術」なるノウハウにも価値が出るかもしれない。
AIとロボットにより窓口業務が円滑になるだろう、という意見もあった。その他の受け答えを要する業務も同様である。現在でも企業では無人受付が主流になってきており(昔は小さな会社でも受付嬢がよくいた)、今後はさらに高度化したAI受付、ロボット受付嬢などが出てくるはずだ。窓口業務も数名のコンシェルジュがいるだけで、その他はAIとロボットが受け持つことになるだろう。とくに業態が激変している金融系はその導入が急速なはず。
最後のチームは、仕事とAIについて「心」という観点からまとめた。システムエンジニアやマネージャーの仕事に「心」は重要である。一方で情報を収集してAIで自動化し、業務を最適化することもできる。であれば、AIに任せられることは任せ、人間は心の要素に集中することで、仕事の価値が高まるのではないか。力石氏の発表にもあったように、人間にしかない精神面、心の領域は、AI時代、今後さらに評価されてくることは間違いない。
AIが人間に投げかけた「問い」を突き詰めて考える時代が来た
チーム発表が終わり、最後に両者からの見解が発表された。
◎最後にまとめるスピーカーの橋本氏と力石氏
橋本氏は、AIと人間が対話できる時代になり、それにより「AIが心を持つことはできるのか」という議論にまで議論内容が進化している。その過程で「人間はなにをすべきなのか」という新しい「問い」が生まれている。その問い自体が、AI時代の人間を進化させる価値ではないか、という。
力石氏はこれを受け、人間とはなにかという定義が改めて問われ、いままで人間ならではの技能と思われていたものがそうでなくなってきた。昔は田を耕せない人は人間ではなかったし、子どもはある年齢に達するまで人間ではなかった。いま、人間を取り巻くルールやゴールが変わり続け、こうした問いがたえず下されている。人間とはなにか、心とはなにかを、さらに突き詰めて考える時代になってきている、という。
* * *
サービスを提供する産業界のエキスパートと、アートと科学の融合のエキスパートの二者によるセミナーは、一見別方向ながら、両者とも「心」という抽象度の高い領域に交点を持ち、高い関心を示されていた。
「AIとロボットに未来はあるのか?」というテーマの回答としてお二人の見解を総合すると、「自分たちがどう生きるか」に尽きるのではないか。言い換えると、受け身で生きられる時代は終わった、である。
「人間を取り巻くルールやゴールが変わり続けている」という意味で、かつて「市民」という概念はなかった。フランス革命以降にこの概念が登場し、モラルを持って都市という共同体の中で協調しあいながら生きていく人間の姿が、市民として描き出された。現代人の感覚では至極当たり前だが、過去にその感覚は存在しなかったのだ。
都市の出現と同じく、AIとロボットの出現で、新しい「市民」の概念ができつつある。それが一体なんなのかはまだわからないが、一つだけはっきりと言えるのは、各人が「自分たちがどう生きるか」を持った人物像が、これからの社会を担う市民である。
「自分たちがどう生きるか」を持つには、自問自答を繰り返す必要がある。自問自答とは、言い換えれば、哲学である。これからの時代、人はますます哲学的にならざるをえない。本セミナーの場が、こうした人々の意識の変革や共有に寄与できたら幸いである。
三津田治夫