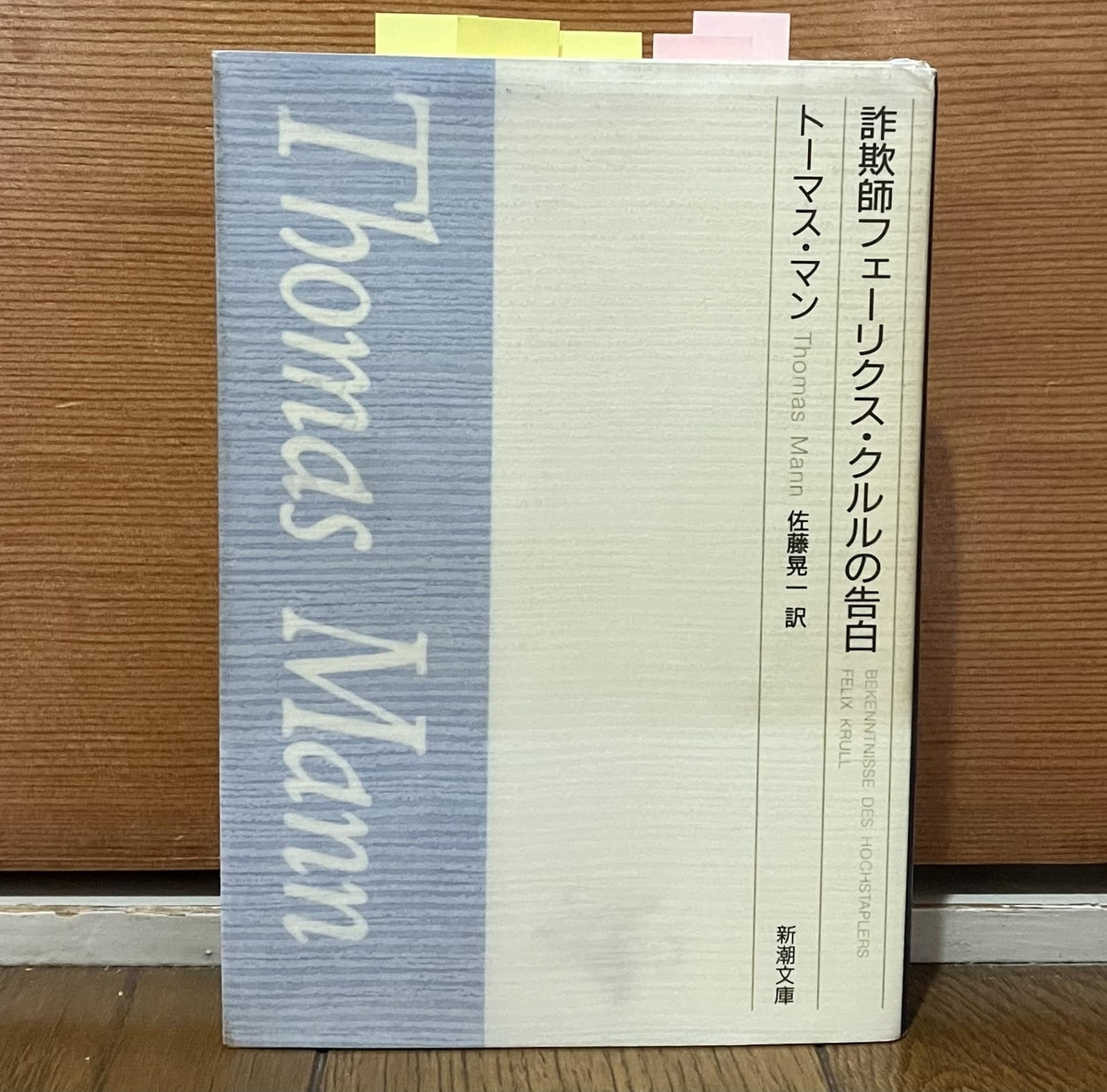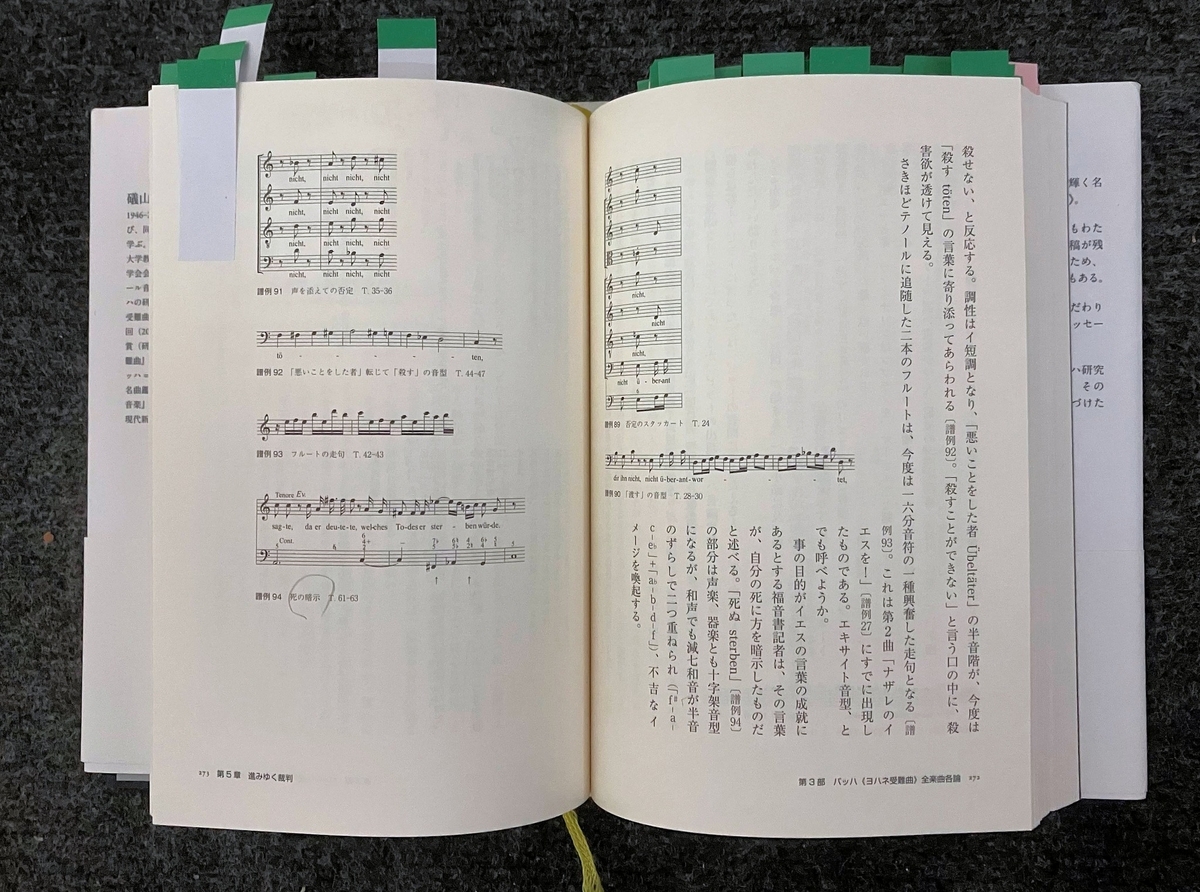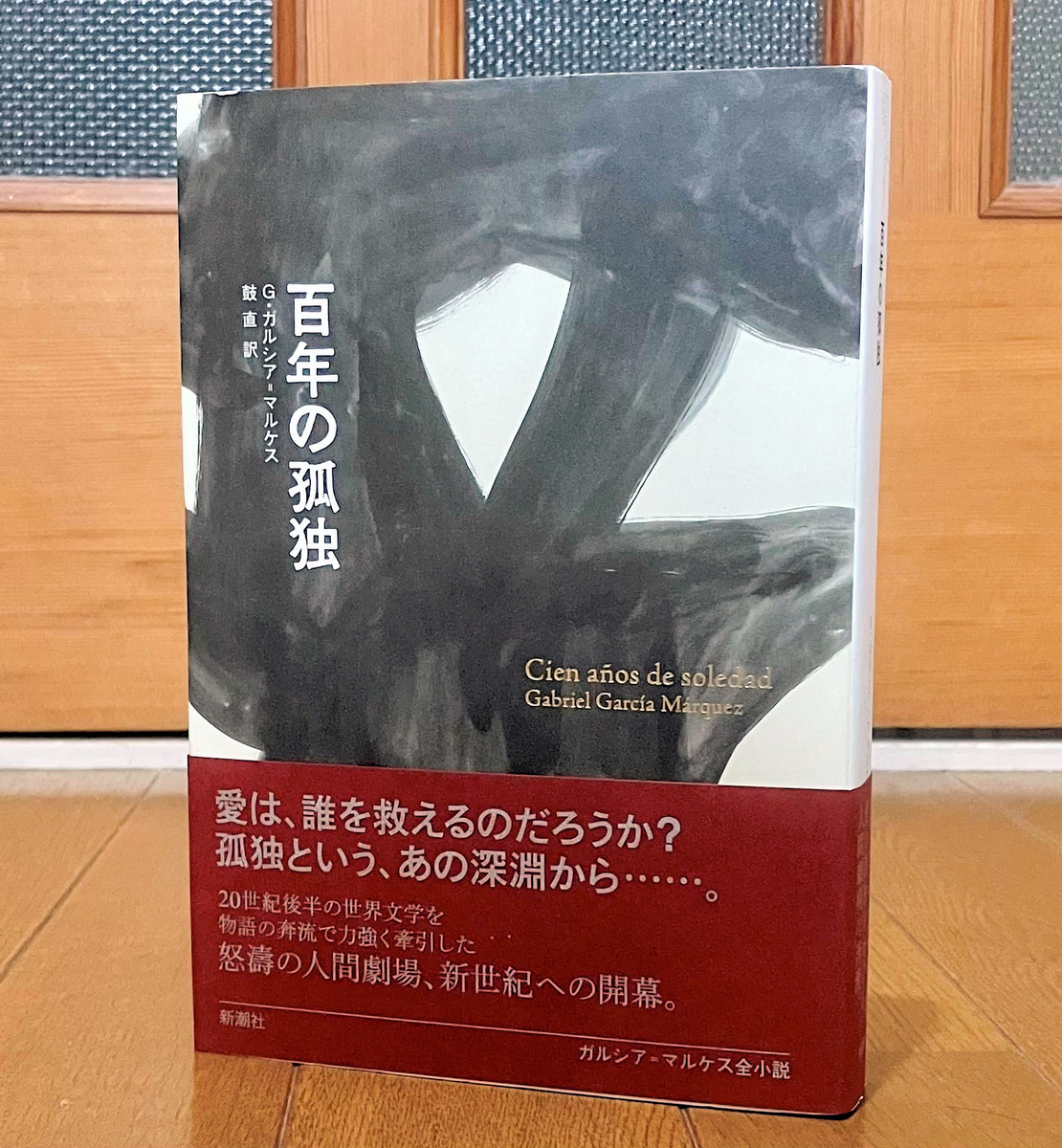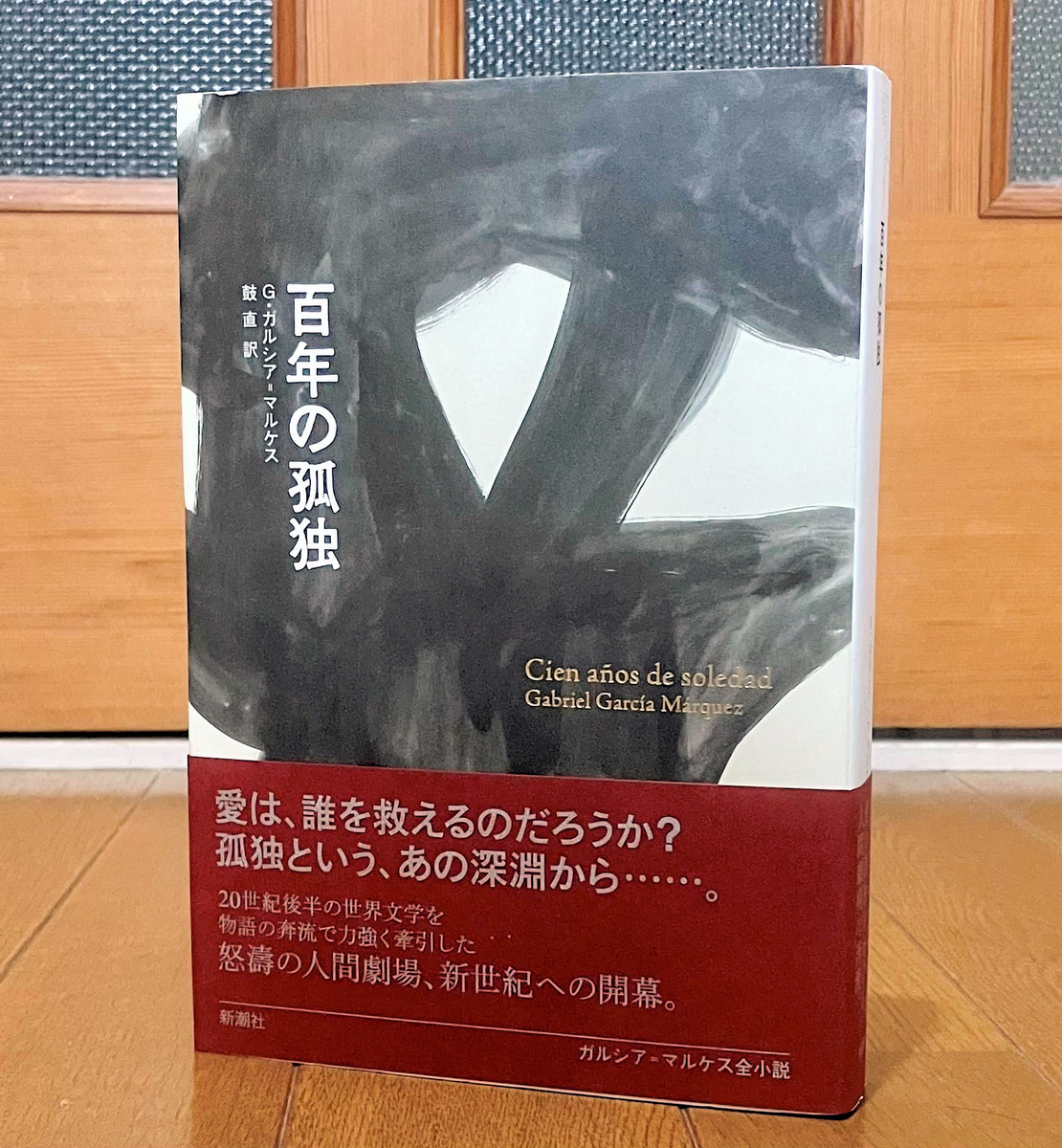
前回の『昨日の世界』(シュテファン・ツヴァイク著)と打って変わって、今回は南米コロンビアのノーベル文学賞作家、ガルシア・マルケス(1928~2014年)の代表作、『百年の孤独』(原作1967年発表。日本発表1972年)を取り上げた。
架空の町マコンドを舞台にブエンディア一家が繰り広げる7代記。
キャラが立った男女が多数入り組んで登場し、死んだ登場人物が復活したり、豚のしっぽを持った子供が近親相姦で生まれてきたり、不思議なエピソードが群れをなす100年の物語。
「魔術的リアリズム」「世界文学の時代を画した超名作」といった評価が世界を取り巻き、Web上でも多数の書評エントリがアップされている。いわば、古典である。
否定はダメだが、右ならえもダメ。権威のある古典だからといって「知ったか」をこかずに読み手の正直さを尊重する本読書会において、新しい世界観を文字構築した本作品に深い敬意を表しつつも、告白すると、個人的にはあまり響かなかった。
権威のある古典がなかなか響かなかった過去事例として、ポーランド文学の巨匠、ヴィトルド・ゴンブロヴィッチの『フェルディドゥルケ』があった。「超面白い」とある方から強く推薦されて3度読んだが、面白みがほとんどわからなかった。
類似の感覚を、『百年の孤独』からも今回は得た次第だ。
南米文学では、こちらもノーベル文学賞作家、マリオ・バルガス=リョサによる『密林の語り部』は面白く読んだ。幻想文学や推理小説の趣があり、興味深く一気に読んだことを覚えている。
もう一つ、響きづらかったのは、マルケスの作品として初めて手にした『物語の作り方』の印象が、個人的には強すぎた点があげられる。
テレビドラマの脚本を作るドキュメンタリー形式の作品で、とにかく視聴率を稼ぐストーリーを作りましょうといった調子が面白かった。「マルケスってこんな実利主義者だったのだ」と感心しながら、文筆のプロ中のプロの言葉に深く共感を抱いた。
同時に、文学とエンタテイメントの古くからの深い関係も想起し、売れる小説づくりや、観客への効果の高い舞台づくりに心血を注いだヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの仕事を思い出した。
そのあとに『戒厳令下チリ潜入記―ある映画監督の冒険』という作品も読んだが、タイトルの通り、『百年の調独』とは趣向を異にするジャーナリスティックな内容だった。

「掴み」が随所にある作品
今回の参加者は、KN、HN、KM、HH、SK、KA、KS(敬称略)、と三津田の計8名。
『百年の調独』に関し、今回、会場からはどのような声が上がってきたのだろうか。
「さらっと読んだ時点で、すごい面白いと感じた」
「物語の「掴み」が随所にある」
といったポジティブな意見が大半だった。
一方で、
「全然面白くない。1980年代の「知的ブーム」の産物だ」
「スラスラ読めたが印象がうすい」
「コミック的」
と、いささかネガティブないしブームの産物という意見があった。
1980年代はニュー・アカデミズムや非西洋の価値観といった、いままでにないものに焦点があてられた時代だ。
このころ「『百年の孤独』を読んだぜ!」と自慢する同級生もいた。
マルケスという南米出現の知、といったところに新鮮味があったのが本作である。
「面白いと思ったが「どう語るの?」と迷ってしまった」
「行動で表現されている」
と、自分の言葉で人に伝えることが難しい本作の作風を指摘する声もいくつか聞こえてきた。
「3回目のチャレンジでやっと読めた!」
というように、読者を選ぶ本作の特性を率直に口にする参加者もいた。
『伝奇集』でおなじみの南米の大作家ホルヘ・ルイス・ボルヘスの名前も会場からは聞こえてきた。
「ラテンアメリカ文学において「カリブ性」の有無が重要。それのないアルゼンチンのボルヘスとは類似性が少ない」
おばあちゃんがとくとくと語る「物語」である
『百年の孤独』には中心が見えない。
私の、つかみどころのない作品に対する印象のおもな動機がここだ。
そんなことを会場で口にしていたら、ふと、KSさんの口から、
「おばあちゃん語りの本」
という発言があった。
つまり本作は、おばあちゃんがとくとくと語る物語である。
確かに、物語には中心がない。
中心にあるものは、ウルスラという本作の核をなす女傑である。
以下、本文から引用する。
====
アウレリャノ・トリステが机の上で描いてみせた図面ーーそれは、ホセ・アルカディオ・ブエンディアが太陽戦争の計画書に添えた図解を思いださせたーーを前にしてウルスラは、時間というものはぐるぐる回っているという、ふだんの印象をいっそう強めた。
====
物語だから、話は円環する。
日本人になじみが深い物語に『源氏物語』がある。
絶世の美男子を主人公に、命が生まれ、恋が生まれ、そして命が生まれ、死んでいく。
それが延々と繰り返される。
生と死と恋愛の物語だ。
語り部はおらず、生と死と恋愛という一本の柱を軸に、物語が円環していくのだ。
物語文学といえば、以前、イタロ・カルヴィーノの『見えない都市』を読書会で取り上げたことを思い出した。
はじめも終わりもない、奇妙な物語だった。
最後に『物語の作り方』から、マルケスが自身の作品観を示した私の好きな一文を紹介する。
======
ものを書く時は、セルバンテスよりも自分の方が上なんだと自分に言い聞かせないといけない。
とにかく理想を高く掲げて、一歩でもそれに近づこうとすることだ。
それに、しっかりした考えを持つこと。
削除すべきものを削除し、他人の意見に耳を傾けて、それについて真剣に考えるだけの勇気を持たなくてはいけない。
そこから一歩踏み出せば、自分たちがいいと思っているものをいったん疑ってかかったり、それが本当にいいものかどうか確かめられるようになる。
======
* * * *
次回はさらに趣を変えて、ほぼ議論することなく、KNさんの鶴の一声で、『アラブが見た十字軍』(アミン・マアルーフ著)が課題図書として選定された。
昨今のパレスチナ問題への関心から、イスラム関連の著作を読んでみたいという声が、そもそもの発端だった。
歴史は勝者が作るものだ。やられっぱなしのアラブから見た白人による十字軍遠征は、どういった戦争だったのだろうか。
次回も、お楽しみに。
三津田治夫