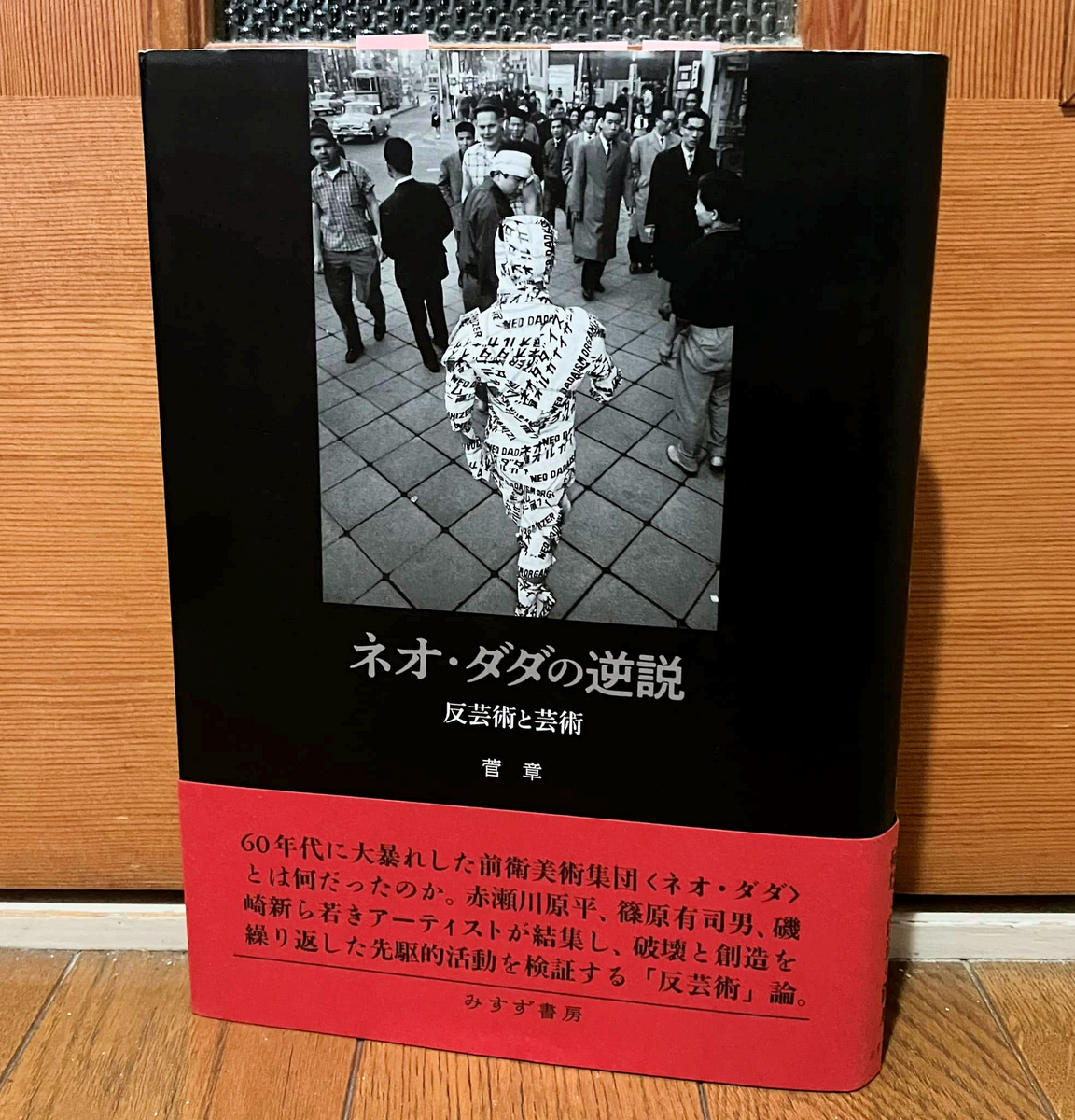2023年ラストの飯田橋読書会は、『アラブが見た十字軍』(アミン・マアルーフ著、 筑摩書房刊)を取り上げた。
アラブが語られる際に、私たちの耳目に入る情報は西洋からのものがほとんどであるが、本作はアラブがいかに西洋から侵略されたのかという逆の視点から描かれた、レバノン出身のジャーナリストによるフランスで出版された歴史書である。
歴史という物語はつねに勝者によって記述される。
ナチスのガス室によるユダヤ人大量虐殺は悪だが、アメリカの原爆による大量虐殺は平和をもたらした善であるという物語は、アメリカという勝者の手で記述されている。
本作は、フランク(西洋人)によって侵略された(敗者側の)アラブ(イスラム諸国)の視点で描かれた、十字軍遠征の歴史物語である。本作の概要は過去のエントリで書いたので、こちらをご参照いただきたい。


イスラムは西洋から学ぶものがなかった
今回は私を含め、KN、KM、HN、KS、SK、KA、HH、SM(敬称略)の計9名の参加となった。
会場から発せられた以下内容を紹介する。
「この時代に生きていなくてよかった。」
「苦しい、厳しい内容。」
と、流血が絶えないアラブのこの1000年を、本作で改めて見た印象が聞こえてきた。
宗教とマネーの歴史の源流を見た
「狂信と富の物語である。」
という発言や、
侵略者が地域を征服し敗者を差別する
「フランクによる“アジア・アラブ差別”の物語。」
という発言も印象的だった。戦争の文脈は連綿と繰り返される。
「日本人ってなんだろ? という疑問を与えてくれた。」
多くの人種や宗教が入り乱れ、しかもこれらが陸続きで共存しながら戦争を繰り返すという、日本列島というなかば要塞の中で生きてきた日本人にはまったく想像がつかない世界観が、本作の舞台となるアラブ諸国において繰り広げられていた。
「よくわかっていなかった十字軍遠征が、ようやくわかってきた。」
十字軍遠征とは世界史の授業で耳にしたがその内実はよくわからない、という人は大半だろう。上記の、日本人には想像もつかない世界観ゆえでもある。
「支配者はいったい何人殺すんだよ!!」
「キリスト教の理論で略奪が正当化されている。」
「クリスチャン以外は殺してよいという理論はいかがなものか。」
皆殺しが正当化される理論構築を再確認する声もあがった。
人が人から命を奪うことは、悪である。
しかし戦争には必ず、「自衛のため」「食糧難克服のため」「世界平和のため」といったビジョンとミッション、すなわち理論化された大義が必要となる。
大義のもとで殺戮と侵略が繰り広げられた宗教の歴史が絵巻物のように描かれていた。


「欧米以外から出た情報を知ることは大切。」
と、事実を知るために敗者からの情報は貴重であり、
「こうした史実が残るので「歴史家」の存在は重要である。」
とあるように、史実とはさまざまな方面から得ることで初めて解像度の高いイメージをなす。
「宗教都市エルサレムは、いまでも現存しているのがすごい。」
戦争による大量破壊で跡形もなく消滅してきた宗教都市は、歴史に残っていないだけで数知れないはずである。その意味で歴史とは、「文字」であるのかもしれない。
「本作をまったく理解できない」という声があがっていたことに関連し、
「人名・地名など、イスラムの個有名詞を読み解くのが厳しかった。」
という声もあった。ロシア文学も登場人物の名前でわからなくなってしまう人は多いが、類似の混乱がこのイスラム史を読み解く際にも発生する。

「前半が混とんとしていてむしろ面白かった。」
前半にはヒーローやカリスマが登場せず、
「イスラム間での連帯がないのが不思議。」
という意見からも、彼らの間に疑いと争いが絶えず、
「シーア派とスンニ派対立の源流が良くわかってきた。」
という歴史認識の背景に「連帯がない」ことは発見だった。
逆から見ると、西洋人はさまざまな人種や言語で構成されていたのにもかかわらず、キリスト教という一つの旗印のもとで連帯していたところが要点である。
そう考えると、聖書は文字の経典でコーランは音の経典であるという相違にも注目できるし、プロテスタントの出現は、一つの旗印を乱す存在としてバチカンに脅威を与えたことも再確認できた。
「温暖化して生産力が上ったアラブ諸国を侵略した十字軍は、言い方を変えたら“フロンティア”ではないか?」
南北米大陸の原住民インディアン、インディオたちから見た西洋人は侵略者であり、西洋人は自らをフロンティアと呼んだことと等しい。
「そもそもイスラムはフランクから学ぶものはなかった。」
元々イスラムは文化レベルが高く、古代ギリシャの農耕や建築の技術、それらを支える哲学や数学、天文学などの科学は、実はイスラム経由で西洋人が欧州へと輸入した。現在、科学の中心は西洋であるが、大元はイスラムがその中心だった。
現代に息づく1000年のイスラム・バチカン宗教史
会の発言でとくに印象的だった言葉を紹介する。
「本作は事件史のようだった。“現代”とのアナロジーがある。」
ラストには次のような記述があるように、本作(原著は1983年刊)を1981年のヨハネ・パウロ二世暗殺未遂事件と関連付けている。
==========
恒久的に攻撃されているムスリム世界では、一種の被害者意識が生まれるのを阻止することができず、これはある種の狂信者のなかでは危険な強迫観念の形をとる。
一九八一年三月、トルコ人メフメト・アリー・アージャはローマ教皇を射殺しようとしたのであったが、手紙のなかで次のように述べている。
〈私は十字軍の総大将ヨハネ・パウロ二世を殺すことに決めた〉。
この個人的行為を超えて明らかになるのは、中東のアラブは西洋のなかにいつも天敵を見ているということだ。
このような敵に対しては、あらゆる敵対行為が、政治的、軍事的、あるいは石油戦略的であろうと、正当な報復となる。
そして疑いもなく、この両世界の分裂は十字軍にさかのぼり、アラブは今日でもなお意識の底で、これを一種の強姦のように受けとめている。
==========
メフメト・アリー・アージャについて付け加えておく。
彼は1958年生まれのイスラム教徒のトルコ人活動家で、1979年2月1日にはトルコの有力日刊紙ミリイェットの編集長アブディ・イペクチを暗殺し、逮捕されている。
その後マフィアの手を借りてブルガリアに逃亡。欠席裁判で死刑判決が下されるが、2年後の1981年5月13日、バチカンのサン・ピエトロ広場でヨハネ・パウロ二世に致命傷を負わせ、暗殺未遂で逮捕される。
男のその後の経緯も特殊である。
さらに2年後の1983年、クリスマスの2日後に教皇ヨハネ・パウロ2世は男が収監された刑務所を訪れ、2人は面会した。
教皇は寛大にも「私は彼を許し、完全に信頼できる兄弟として話しました」と語った。
2005年4月に教皇が死去。これを知った男は悲しみ、「2007年5月13日をもって、私はイスラム教の信仰を捨て、ローマ・カトリック教会の会員になることを決意した」と、キリスト教に改宗した。
2010年には約30年刑期を終え釈放。釈放後はヨハネ・パウロ二世の墓参に行くが、イタリアから国外退去を宣告され、2014年トルコに強制送還。ハリウッドからは映画オファーがあったというが、その後の消息は定かでない。
『アラブが見た十字軍』の舞台裏では、現代にも通底するイスラムとバチカンの物語が流れていたのである。

『アラブが見た十字軍』をめぐる参加者たちのやり取り
本読書会は、メンバーに開催期日を事前にメール調整するのだが、その際に選書の感想や疑問のやり取りも行われる。
今回は密度の高いやり取りが行われたので、本人たちの許諾を得たうえで、以下にその内容を記録・参考として掲載する。
==========
みなさま
SKです。
ヘルプ!
『アラブが見た十字軍』、わたくしこれ劇的に苦手です。
理由はいろいろですが、内容的にどうのこうのというよりも、書き方がちょっと……。
現在340ページくらい、いまのペースだと当日までに読み終わる自信がありません。
そこで、おもしろかった、とか、こう読んだらいいとか、どなたか、なんとか最後までたどり着くためのヒントをお持ちの方、お教えください!
==========
==========
KSです。読みにくいの同感です。
わたしもいま300ページを超えたあたりですが、当日までにぎりぎり読み終わるかなという感触でいます。
自分の場合、地理を確認するために毎回スマホでウェブ検索していたのが読むのに時間がかかっていた一因だったのですが、半分くらい読み進めた時点で巻末に地図があることに気づきました。
また、要所で引用されるアラブ歴史家が複数いることにしばらく気づいてなくて迷子になったので、いったん最初に戻って各アラブ歴史家の初出をピックアップしてたりしていたら、少し見通しがよくなった気がします。
参考までに、300ページくらいまでに出てきたアラブ歴史家メモです。
- イブン・アル=カラーニシ:p.25 ダマスカスの年代記作者。ダマスカスで暗殺教団がトゥグティギンの息子ブーリにやられたころは57歳(p.201)
- イブン・ジュバイル:p.23 スペイン出身のアラブの大旅行家。侵攻開始から1世紀後にパレスチナ訪問
- イブン・アル=アシール:p.54 アラブの歴史家。フランクの侵入の初めから1世紀以上も後
- モースルの史家:p.144
- カマールッデイーン:p.174 アレッポ出身の作家にして外交官。アレッポ動乱(1113年ごろ)から1世紀後
- ウサーマ・イブン・ムンキズ:p.232 ウナルの友人の年代記作者
あと、これは本書を読む助けになるかは微妙ですが、同時代のビザンツを描いた『アンナ・コムネナ』という漫画が、自分にとって「フランクとアラブの間にいたビザンツは何をしていたか」をうかがい知る補助線になってます(本書に出てくるフランクの諸侯や地名も当然ながら出てきます)。
https://sai-zen-sen.jp/comics/twi4/annakomnene/
もうひとつ、これは本書を読む助けにならない情報ですが、アラブがモンゴルの襲来を受けたときのイスラム世界から話が始まる『天幕のジャードゥーガル』という漫画があり、この漫画の世界に本書のアラブ世界がどうつながっていくのかが自分にとって本書を読むモチベーションになってます。
https://souffle.life/author/tenmaku-no-ja-dougal/
==========
* * *
次回は、さらに趣向を変え、久しぶりのアジア文学へと向かうことにする。
韓国人で初の英国マン・ブッカー賞を受賞した作家、ハン・ガンを取り上げる。彼女の作品から、『少年が来る』『すべての、白いものたちの』『菜食主義者』など、主要なものが俎上に上がる。文学を通してハングルの世界観をいかに共有できるか。次回も、お楽しみに。
三津田治夫