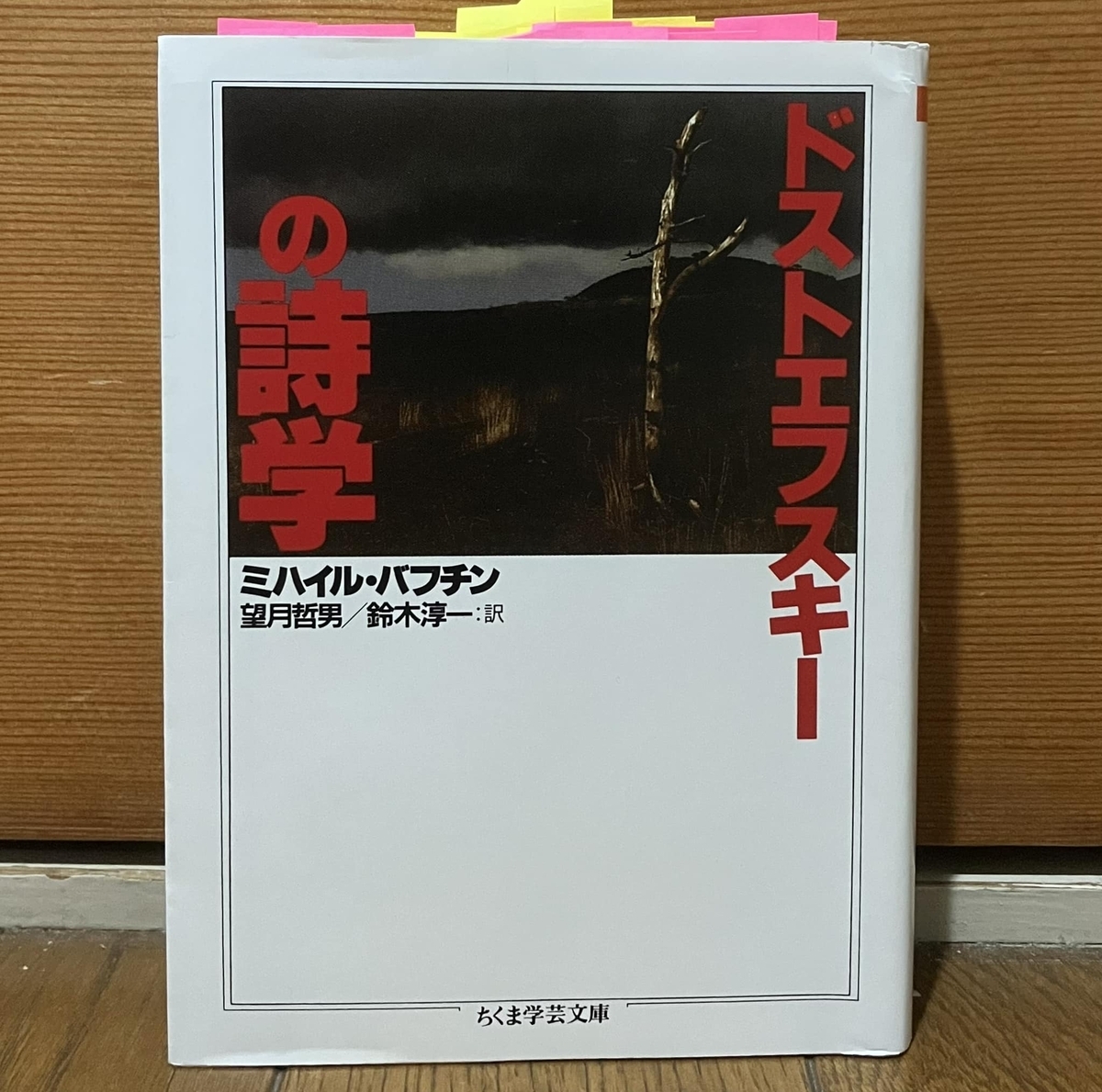
いわゆる評論とは、「〇〇主義」や「××説」、「□□論」という引用やひな形が論調のベースに敷かれることが多い。
しかし本作はそうではない。
ドストエフスキーが書き記した言葉そのもの、言語そのものに迫り、彼の作品の本質に迫る、共感が多い文芸評論である。
とくに本作発刊当時のソビエト連邦時代は、著作の方向性が、
「社会主義は平等ですばらしい」「貧困を冗長する資本主義はダメだ」
という社会主義共産主義礼賛論調でないと、発刊は困難だった。
ドストエフスキーですら、社会から虐げられた貧困層のすさんだ心や犯罪を描き、「資本主義の悪を捉えた作家」ということで、ソビエト連邦時代にいたっても芸術家としての存在が国家から認められていた。
バフチンの評論は、国家や「主義」「説」「論」に一切与しない。純粋に言葉にしか関心を持たない評論である。
ドストエフスキー作品の登場人物の各々が発言する「声」が、あたかも多声音楽(ポリフォニー)を織りなすように大河小説をつくり上げているのだ、という内容。
心理描写や思想的な主張、推理小説な展開がドストエフスキーの面白さだといえるが、登場人物の声に焦点を当てたところに本作の魅力がある。
原文のロシア語で読んだら、相当迫力があるに違いない。
『罪と罰』『カラマーゾフの兄弟』『悪霊』『分身』といった、彼の人気作品を中心に取り上げており、これらに接したことがない読者にとっても、「一度は読んでみたい」と思わせる引用と解説が親しみやすい。
ぜひ一読をお勧めする。
三津田治夫